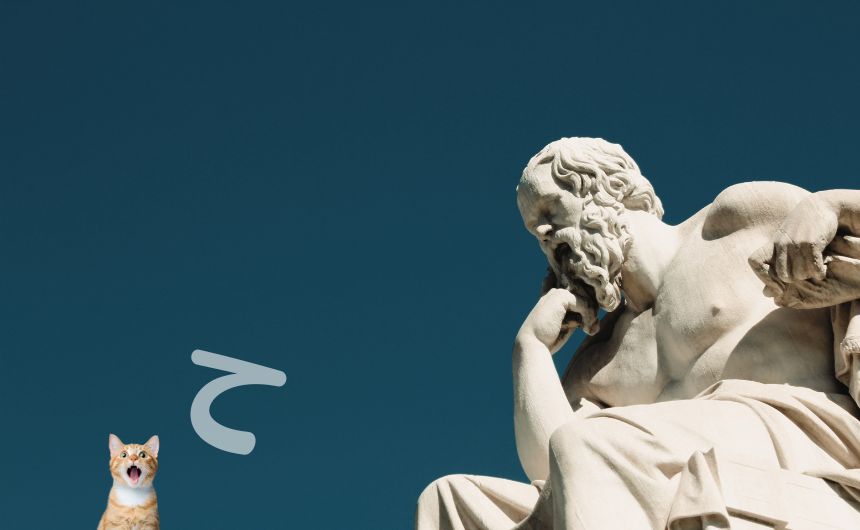はじめに
どの分野にも老害はいる
老害は年齢ではない
こんにちは🐻sakiパパです
哲学は猫に関係ないと思っている方もいるかもしれませんが関係大ありです
哲学は学問ではなく「問い続ける営みそのもの」
だから正解も間違いもありません!
そしてほとんどの猫界隈の住人は考えているようで常識やこれまでの経験に縛られ過ぎて問いを立てていない。
「こうかもしれない?」
「なぜ○○何だろう?」
「どうすればいいんだろうか?」
・・・・
この問いが大事でそれは時代によっても変わります。
なので哲学の本質を知ってもらって、学ぶんじゃなくて「意識」してみて
欲しいんです。
そのための
哲学の本質とズレみたいなものを少し整理してみました!
「哲学は学問じゃないから難しくない!」
普段から実はみんなやっているのに気づけていない
もっと意識すればもっと気づけるのに素通りしてしまっている
それが哲学です😺
1. 哲学という言葉の原点
語源はギリシャ語 philosophia(知を愛する)。
本来は「知者(賢者)」ではなく 「知を求め続ける者」 を意味した。
哲学の本質は 答えを知ることではなく、問い続ける「謙虚さ」にある。
2. 日本での「哲学」イメージのズレ
明治期に「philosophy」を「哲学(智慧を探求する学問)」と訳したことで、権威的で難しい印象が強まった。
哲学=学問、哲学=知識の蓄積、という誤解が広がった。
結果として「哲学=一般人には関係ない難しいもの」と思われやすくなった。
3. 知識モンスター化の問題
哲学に関わる人の中には「複雑に語るほど深い」と考える人もいる。
その結果、日常から切り離され、専門用語や哲学史の羅列に終始する。
本来の「知を愛する態度」が、知識のひけらかしにすり替わってしまう。
4. 哲学と哲学史の混同
哲学=「生き方として問い続けること」。
哲学史=「過去の哲学者の思想を学ぶこと」。
本来は別物なのに「哲学をする=哲学史を知っている」という前提ができてしまった。
哲学はまず 日常を哲学的に生きること、興味があれば史学に進めばよいだけ。(ソクラテスやカントも1サンプルに過ぎないから別に知らなくてもいい)
5. 哲学対話の誤解
本来の哲学対話
その場で自分が感じていることや違和感を率直に投げかける。
「私はこう思う」→「なぜそうなんだろう?」と問いを広げていく。
知識は材料の一つにすぎず、問いを生むことが目的。
結論を出す必要もない
よくある誤解
哲学史や知識を披露する場になってしまう。
「正解」を探してしまう。
知識のある人が場を独占して、他の参加者は黙ってしまう。
6. 哲学を取り戻すために
哲学は 日常にある「なぜ?」を意識すること。
哲学対話は知識披露ではなく、問いを共有する場。
哲学史は「必修」ではなく「選択」でいい。
まとめ
哲学は「知を愛する=知りたいという気持ち」から生まれた。
本来は誰にでも開かれた日常の営みであり、特別な学問ではない。
哲学は答えを出すことではなく、問いを残すことを楽しむこと。
哲学はもっと身近で、豊かな営みになるはずだ。
私は学校の教育の一番最初に哲学を置くべきだと思っている
哲学はいろいろな学問とともに海を渡ってきた?!から学問の始まりという概念を持っていない方もいると思うがすべての学問の本質は探究から始まっていると私は考えており、何に使うか使えるかわからないけど気になるから研究してみるから始まっていることも少なくない。
だから元をたどれば、哲学的な営みから始まったのが学問と言い換えても間違いではないと思う。
哲学的な考えは、いろいろなコトを深堀していくし、これまで当たり前だと思っていた常識を疑うことも少なくない。
みなさんは日常で常識だと思うことをどれだけ疑っているだろうか?
- 目の前にある気になることを探究する
- 哲学史を知る
- 哲学に生きる営み自体を構造的に研究する
・・・
様々な意味の異なることを一緒に「哲学」とまとめてしまった上に
後の哲学を学んできた層が、哲学史を哲学のマウント利用している構造などが重なり
私が皆さんに持ってほしい「哲学」をかなり複雑にしてしまっている。
私の言う哲学は学びではなく、自分の問いです。
なぜ朝は来るのだろう?でもいいし
なぜ朝礼はしなくてはいけないのだろうでもいい
こうすればいいのに、でもこう変えたらこうなるかもしれないとか
本当にこれは正しいのか?・・・・と問い続けること疑い続けるコト
つまり常識を固定しないことともいえるかもしれない。
さらに、概念工学とも相性が良くて、一つの問いからこれまでの概念を分解して、深く深く深堀して、再構築して概念を変化させる
そうすることで猫のボランティアも大きく変わっていくと私は考えています。
私がこれまでしてきたミルボラはまさに哲学と概念工学の掛け算のようなもの。
日常やこれまでを違った角度から見たり、疑ってみたり、仮説を何個も立ててみて、実証したり熟考したり概念そのものを変えるための行動をしていく。
すぐには変わらないかもしれないけど、考える人が増えてくれば来るだけ、もっといい概念に生まれ変わります。
その一歩は「生活に問いを意識すること」
みなさんもホントはたくさんある目の前の問いに目を向けてみませんか?