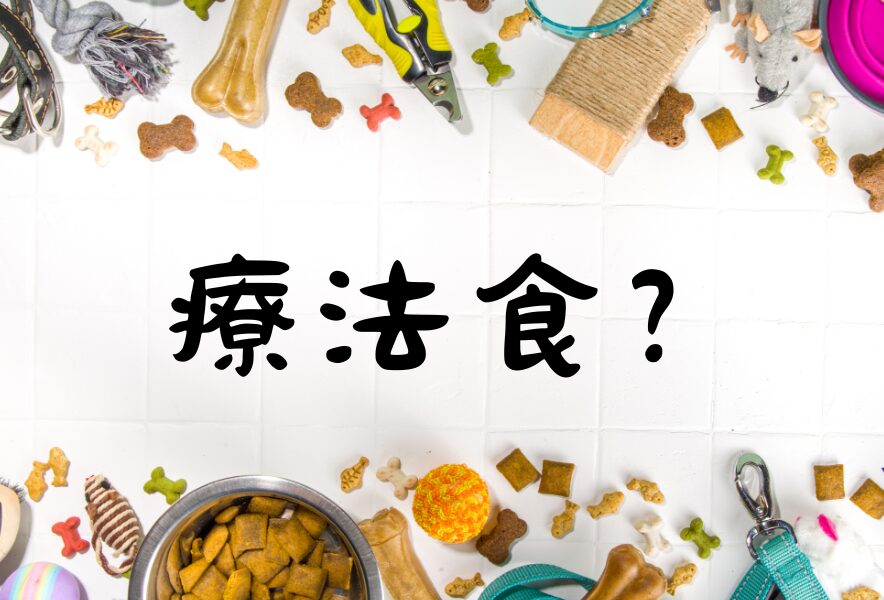近ごろ、「保護猫」という言葉をよく耳にするようになった。
けれど、その中には「保護」とは呼べないような仕組みも増えている。
たとえば、ペットショップやブリーダーが、
売れ残った猫を「譲渡」という形で手放すケース。
「経費」として4万円前後を請求し、販売ではないと主張する。
また、ビジネスとしてペットショップから猫を引き取ってきて、
「保護猫」として再び「譲渡(経費という形で金銭を得る)」する例もある。
こうした行為が悪質だと非難されがちだが、問題はそれだけではない。
ペットショップやブリーダー自身も、
「経費請求」という名目で譲渡を行い、
実質的には「販売の延長線上」にあるケースが少なくない。
この構造そのものがグレーであり、
言葉の使い方ひとつで「ホワイト」にも見せられる。
かつては、売れ残った猫が「引取り屋」に渡され、
劣悪な環境に置かれたり、
法改正前には愛護センターや保健所に持ち込まれることもあった。
つまり、この「譲渡という言葉の利用」は、
古い構造を形を変えて延命させているだけかもしれない。
一方で、買い手にも理由がある。
「ブランド猫は高いけど、保護猫なら」と、「お得な善意」で行動してしまう。
しかしその善意が、偽りの保護を支える市場になってはいないだろうか。
私は思う。
この問題は「業界」ではなく「人」の問題だ。
もちろん、ペットショップやブリーダーの中には、終生飼養を見据え、命を尊重した繁殖・販売を行う人たちも多くいる。
同じように、ボランティアにも真摯に命と向き合う人たちがいる。
つまり、
★★悪いのは「業界」ではなく、「倫理を欠いた一部の人間」★★なのだ。
そして最後に一つ、はっきり伝えたい。
「ボランティア=良いこと」とは限らない。
「販売=悪」とも限らない。
★★大切なのは「行為の名」ではなく、その「内側にある意図」★★だと思う。
法律が変わる前に、
モラルで「それは違う」と言える人が増えること。
その意識こそが、猫たちの未来を守る、ほんとうの「保護」につながっていく。